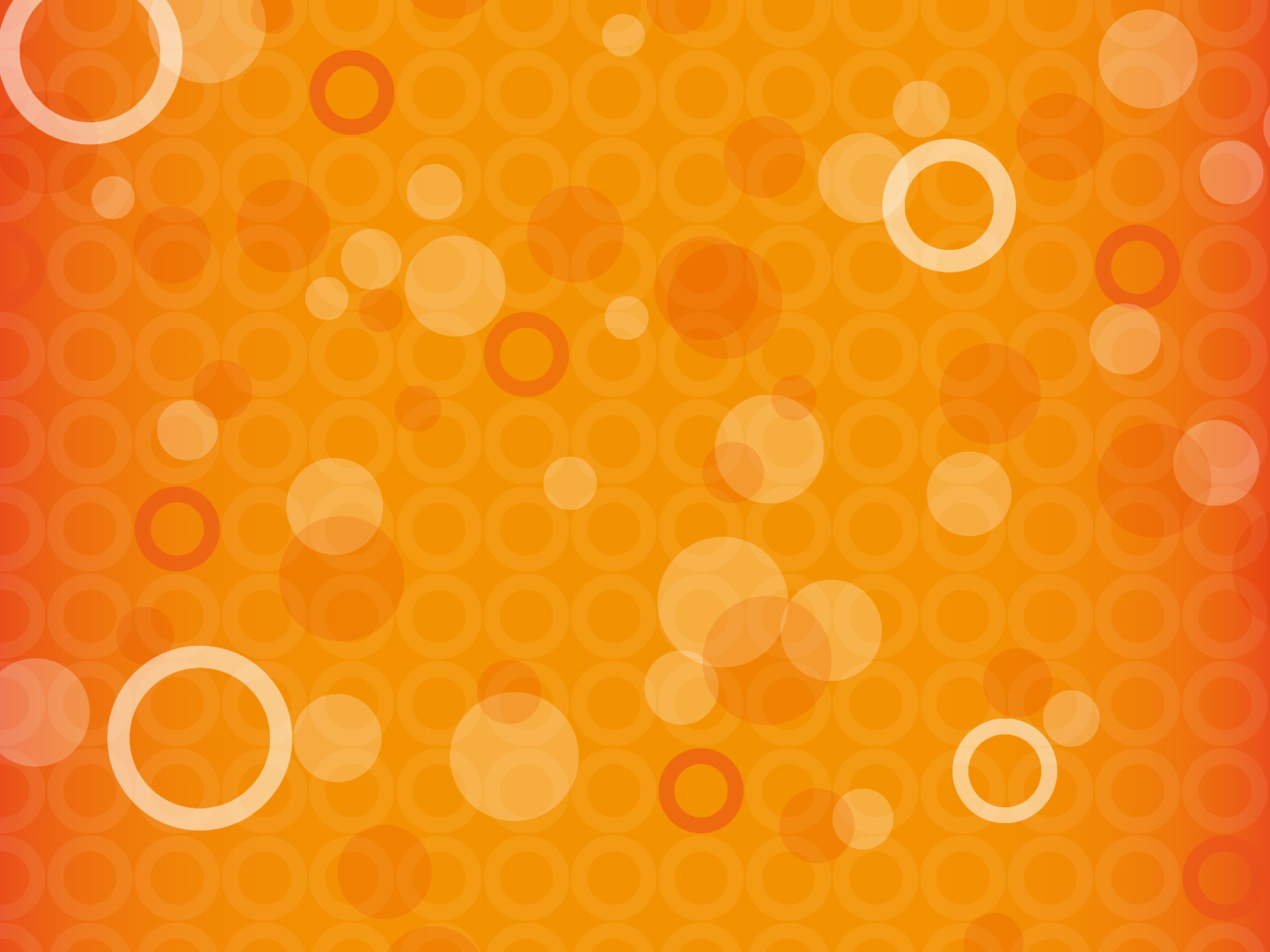経済学
(2024.3.14 〜)
本経済学は、中古品と仮想世界の経済理論を扱うものである。
仮想世界とは仮想空間の事であり、ゲームで行われるような仮想空間のイメージである。
中古品に関しては、中古使用観や部屋の占有率等から中古品を分析するものであったが、まず、仮想空間の経済理論について触れよう。
これは、仮想空間というのは、製作者サイドの意思が自由に反映するわけだから、経済に関しても需要と供給のバランス関係を見守るというよりも計画的に設計すべきである。仮想世界の「神の手」は製作者であるから。バーチャルアイテム(仮想道具)に関しては、プレイヤー側からの需要に任せて適時供給を行うと言っても、単に製作者側が増やしたいと思えば供給品をコピーすれば良いだけ。仮想ダイヤモンドでもコピーすれば事足りる。
よって、社会主義国家の統制計画経済を参考に仮想空間の経済市場の統制手法を構築していく。
故に、まず、価値とは労働によって産み出される。「価値=労働」である。
*本学の基本方針が、例えば、マルクス『資本論』等を仮想世界の学へと転用する、という基本方針が示された、と解して良い。
これは、現実的には、その仮想物品のデザインに要した時間という事になろうが(車でもバックでも書いて起こす)、ここは統制的に、「労働時間」を個々の仮想物品に計画的に割り振り、物品価値を誘引するベースとする。
このバック 〜〜労働時間
あの車 〜〜労働時間
また、プレイヤーの側と、仮想物品の作出行為を協業で行うようなケースだと、上の基本方針より、プレイヤーの現実労働時間に配慮すべきである。
例) 企画であの仮想バックをプレイヤー側と一緒に制作しよう、というものがあったとして、価値は労働より生み出されるので、実際にプレイヤーに時間を使ってもらう等の配慮が必要。
さらに、需給関係を考えて、需要が発生すると、単にコピーして増殖させるというのでは物品価値も産まれないので、価値を産むためには生産個数管理が必須である。仮想物品にシリアルナンバー配布やペーパーの鑑定書発行がその手法となる。故に、上記労働時間と矛盾しないようにしなくてはならない。すごく生産労働時間がかかっている車なのに、やたらと個数が多いと、時間的に矛盾する。
「アイテムの価値の半減期」について
仮想物品に限った話ではないが、現実の物品も含め、全ての物品は基本的に「価値の半減期」を有するもの、と決めてしまう。当然、現実には放射能の半減期のように価値が規則的に減ってはいかないだろうが、こういうふうにまずは決めてしまい、ここから乖離している乖離度が甚だしい、などと評価を行う土台とする。そして、その半減期の決定方法としては、ネットによるアンケート調査集計により決定される。感覚的にマスではどのように価値減衰のイメージを捉えているのか?という事だ。
例) (半減期を有するとして)
このバックの半減期は?
あの車の半減期は?
このアンケートには、生産必要労働時間を盛り込んだ問いも織り交ぜ、半減期に対する認識への影響を探ると同時に、使用観と半減期との関係性等も考察する。
現実には、全くこの半減期に沿った形には一切ならないし、このような研究に価値はあるのか?という問いに対しては、上記統制計画経済の考え方より、仮想物品の価値はこのように落ちると決めてしまうのである。
これが、仮想物品の「生産年度、年式」の考え方だ。
使用観については、新品と中古品に大別されるはずだから、
新品価値
中古品価値
に分けられる。さらに、中古品価値は、当人価値(新品購入者である本人)と一般価値(本人以外の中古品放出待機者)で考える。例えば、新品の下着販売を考えると、消耗品であることを考慮しつつ50年前の下着の新古品を買いたくないように、価値は未開封であっても減衰する。中古品の場合、当人価値だとどれくらいの半減期か?、一般価値だと、下着の中古品など使用観の観点から全く欲しくないので、
*下品な例ですいません。「好きなアイドルの着用水着ならば欲しい」などという話は、特殊物品のプレミア品に属する話題。
*消耗品は、購入後通常使用が前提です。消耗品の種類によっては始点と終点を決められるものがあるので、例えば、シャンプーなどは、mlに依存して、毎日どれくらい使うとしてそのペースで使えば何日で切れると分かるので、使い終わりの日数までで直線を結べばよい。
気持ち悪いので、中古一般価値は激落ちする。つまり、半減期のy軸の切片位置に影響するはずだ。
まずは、本経済学とは、この「アイテム価値の半減期」のマス調査サーバーの構築から考えなければならないだろう。
計画経済の仮想世界への導入とは、認識価値を計画的にコントロールするという事。元来はアイテムの画像データはコピー出来るし、半減期もへったくれも中古使用観も無い。データーなので劣化しない。
以下 2024.9.8 記
「アイテムの半減期」と言われても「現物商品はそんな半減期特性など示さない」と反論されるでしょうが。「仮想アイテムの場合は、計画的に価値を落とす、産出労働時間を統制するという発想です。これが仮想世界の「計画経済」であって、ロシアとかのそれを転用するやつです。5ヵ年(なのか?)で、このツボを100個算出配給等。仮想世界から現実側を見て、思念(は現実世界より形成される)としては半減期はこうだけど実際の現物アイテムで半減期線に近しい特性を示すのどれかな?と。それが経済学であってテキトーではない。画像データの机は客観視すれば劣化しないデータなので、"計画的に"価値が落ちてもらわないと、又は、使用感等を駆使して中古品の概念を形成しないと困ります。中古品を語ってたけど、仮想世界の経済学からの必然から。
中古品も現実の中古市場をリサーチして中古の理論を作るわけですが、理論的にはこの半減期に依拠するので、この理屈で価値が落ちる、中古品の場合はこの半減期線にこのように影響すると。ここがポイント。中古品の特性を検討して、最終的にはこの半減期線に係数をかけたりして、中古になった段階でこのカテゴリーはy切片に1/2かけるとか。まずもって価値は主観的であるからして、アンケートにより「半減期が前提ということならこの物品の半減期はこれくらい」とそのように回答者が価値を把握しているわけだから、企業戦略に多大な影響を与える学問部署と言えよう。
くどいですが、データや中古市場を調査した結果「現物商品はそんな半減期特性など示さない。そんなものはない」ではなくて、アンケート調査より物品の半減期はこう思う。が本経済学の骨格でありまして、前提を履き違えてはいけない。「そんなものは経済学とは言えない」と反論するのは浅はかだ。例えば、この理論(半減期)と実際に近しい振る舞いを示す現品はどれか、と検討するだけで、立派な経済学だ。そして、仮想空間のアイテムに作用させる手法であるので、なおさら経済学だ。頑なに否定されるとちょっと意味不明というか、この曲線に考案した中古理論より係数をかけるんだって。
わかったけど、それで経済学で賞獲れるのか?と、いや、まあ、あんま自信ないかな…。
このアンケートというのも、ここ数十年のコンピューターネットワークの発達があってこそマス集計出来る訳だろ?、だから、アイテムの価値を管理しているのは本学(又は本社)のコンピュータだ、みたいな感じです。銀行ネタで「コピーバンク」というのもあったけども、あれだって、現実の価値(効用)を仮想世界に流入させることによって、効用を増大化させるという理論よりだったでしょ?「経済の専門家じゃないからテキトーだ」じゃなくて、そうじゃないって。↑どうしてこれが経済学として認められないのよ?と、思うけどね。現実の経済学の理論は中古だと、中古車市場の情報の非対称性とかじゃないの?まあ、色々あるんだろうけど、物品の半減期に関しては無いだろうし、おそらく数年前に私が載せた時点で↑のように否定されてると思うんだよね。